学研教室の卒業生 青木さん

精神保健福祉士
青木 悠
ずっと真摯に患者さんと向き合い続けたい
支援学級から福祉に関心を持った
現在は産休中ですが、精神保健福祉士という国家資格を取得し、精神科の病院でソーシャルワーカーとして勤務しています。病院では相談員と呼ばれることが多いです。
精神保健福祉士は、精神疾患を抱える方が金銭面で困ったり福祉サービスを利用したい場合に、さまざまなサービスを紹介し、窓口への橋渡しをする役割を担っています。
小学生の時に通っていた小学校には支援学級があり、そのクラスの子どもたちと関わりを持ったことをきっかけに、福祉に関心を持つようになりました。その後、ボランティアに行くようになり、さらに大学でも福祉を専攻して精神疾患の分野に関心を持ち、その後、資格を取得して就職しました。
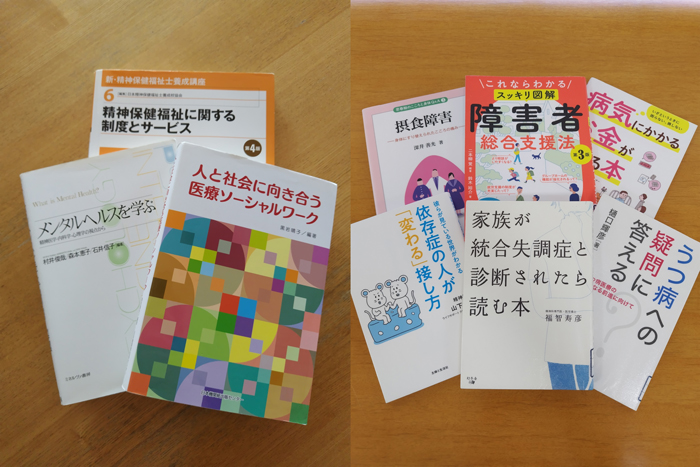
▲青木さんが資格を取得、学びを深めるために活用した書籍たち
自力で解くことで得られた達成感
福井県の学研にしふじ教室では、夏に教室に通っていない子でも参加できるイベントが行われていて、そこに参加したことで教室に興味を持ちました。当時、すでに友達も通っていて、とても楽しそうに感じたんです。当初は勉強目的よりも、楽しい遊び場的な感覚が強かったように思います。
教室には小学3年生から6年生までの約4年間通いました。もともと読書が好きで国語は得意だったのですが、算数などは得意ではありませんでした。ですが、教室では自分のレベルよりも少しだけ難しいプリントを出してくれて、まず自力で解いてみようと思えたのです。先生からヒントなどもいただきましたが、自力で解けると達成感もあり、また理解できたことへの喜びもありました。
スモールステップで教えてもらえたことで、苦手意識を持つ前に問題を解決できて、勉強が苦痛にならずにすんだのだと感じています。また、城下先生やお友達と会うのも楽しく、それが通うモチベーションにも繋がっていました。
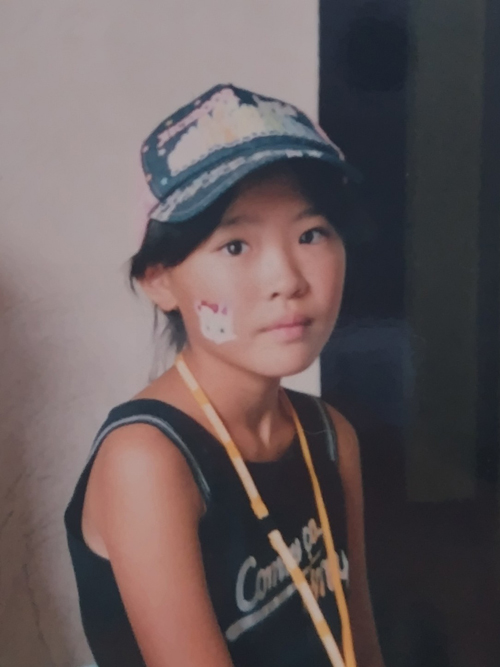
▲子どもの頃の青木さん。教室は年下の子も多く、まわりの子どもたちのお姉さん的な存在だったそう。
自分と違う視点を教えてくれた先生
城下先生は、私から見るととても優しい先生でした。もちろん、宿題をやってこない子どもに厳しく接することもありました。けれど、怖いと思うことはなく、まるで「お母さん」のように慕っていました。
先生は、勉強以外でもいろいろなお話をしてくれました。なかでも、本の感想を言い合えたことが思い出に残っています。私が読書好きだとご存知でしたので、先生が個人的に面白かった本を紹介してくださったんです。私から先生に面白かった本を薦めることもあり、お互いの感想を言い合うこともありました。先生の感想は自分とは違う視点が多く、いろいろな見方があることを学べました。
また、プリント学習の際も、文字を丁寧に描いたり、真摯に取り組んでいたりする姿勢を汲み取ってくださったときには、「ベリーグッド」というひと言と、特別なシールをもらえました。そのシールが一定数貯まると鉛筆に交換してもらえたのですが、丁寧に取り組む姿勢が相手にも伝わるし、それが自分にもいいこととして返ってくるのだと、そのときに学んだように思います。
将来的には、自分の子どもにも難しいことにあきらめずに挑戦し、楽しみながら学べるようになってほしいと願っています。いずれは、学研教室で、学ぶことの大切さや、問題をクリアすることの達成感も学んでくれたらなと思っています。
慣れることなく、常に初心を忘れずに
精神保健福祉士の仕事は、専門用語の示すところや、福祉サービスについて、相手に納得していただくことがとても大切です。自分だけが理解していればいいのではなく、相手にも正しく、わかりやすく伝えるにはどうしたらいいかは、城下先生との会話が礎になっていると感じています。
また、高校や大学受験、国家試験の勉強中は、わからないことにぶつかり、躓くことも多々ありました。それでもあきらめずに取り組むことができたのは、スモールステップで目の前の問題と向き合えば、必ず自分の身になるという経験があったからです。学研教室で学べたおかげで、難しい問題でもいずれ解けると自信を持つことができたのだと思います。
就職して7年目になりますが、今も悩んだり迷ったりすることはあります。ですが、困難な状況にある患者さんが、自分と関わることで少しずつ状態が改善し、ゼロからプラスに向かっていく過程に携われることにやりがいを感じています。これからも資格に関する勉強は絶えず続けながら、真摯に患者さんやご家族の方と向き合いたいです。私にとっては何年経験を積もうとも、目の前の患者さんは初めて会う方が大半ですし、同じようなお悩みに見えても、個人によってまったく違うものです。ですので、慣れることなく、常に初めての気持ちを持って、仕事に取り組んでいきたいです。
